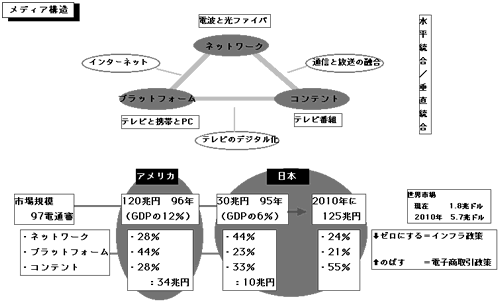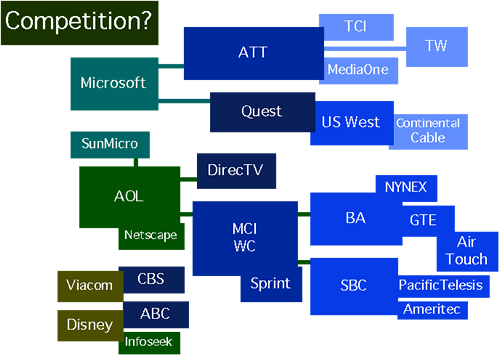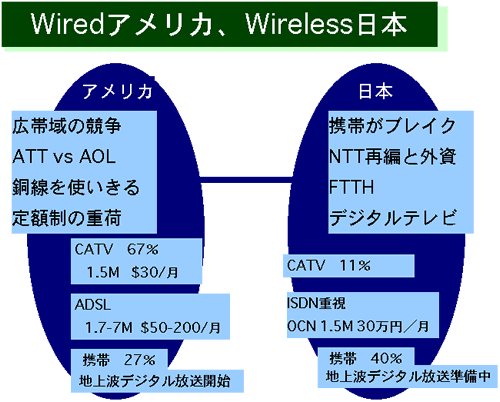|
�@1990�N��̑O���܂ł́A���ꂼ��R�v�f�́u�����v�ŁA�f�W�^���Z�����i�߂�ꂽ�Ƃ������Ƃ��ł���B
�@���Ƃ��l�b�g���[�N�ɂ��Ă����A�d�b�ԁA�ʐM�q���ACATV�ȂǁA�p�r��@�\�ɂ���ăo���o���ȑ��݂ł��������̂��A�@�\�������}����悤�ɂȂ����BCATV�Ƃ����������f�B�A��ŃC���^�[�l�b�g������A�Ƃ����̂��T�^�ł���B
�@�v���b�g�t�H�[���́u�}���`���f�B�A�v�Ƃ������t�B80�N��O���A�e���r���r�f�I��Q�[���@�ƌ������āA�G������@�B����A�C���^���N�e�B�u�ɗV�ԓ���ɂȂ�A�R���s���[�^�ɋ߂Â����B80�N��㔼�ɂ́A�p�\�R����������f�[�^�����łȂ��G�������悤�ɂȂ�A�e���r�ɋ߂Â����B90�N��O���ɂ͂���炪�ʐM�@�\���������B�e���r�ƃp�\�R���Ɠd�b�̋@�\�����킹���f�W�^���@�킪�}���`���f�B�A�Ƃ������O�Ŏs��ɓo�ꂵ���̂��B
�@�R���e���g���f�W�^���Z�p���Z�����ē����Z����i�߂��B�f��Ƃ��Ă̍�i���r�f�I��e���r�ACD-ROM��Q�[���A�Ƃ�����ɓW�J�����u�����\�[�X�E�}���`���[�X�v���蒅�����B
�@90�N��㔼�ɂ́A�R�v�f�ǂ������f�W�^���Łu���ԁv�Ƃ����Ӗ��ł̗Z�����{�i�������B����͍���̐��N�A���₨���炭2010���ɂ킽���Ƃ��đ������ƂɂȂ낤�B
�@���Ƃ��l�b�g���[�N�ƃv���b�g�t�H�[���̌����B�p�\�R���ƒʐM�̖{�i�A���A���Ȃ킿�u�C���^�[�l�b�g�v�̗����ł���B�A�����J�ł̓C���^�[�l�b�g�̓��W�I��e���r�̕��y�𐔔{���鑬�x�ōL�܂�A99�N���ɂ�37���̕��y���ɒB���Ă���B���{���A�����J�ɗ��Ƃ͂���15�����x�ɂ܂ŒB���A�����Ȑ������݂��Ă���B
�@�����ăl�b�g���[�N�ƃR���e���g�̌����B����́u�ʐM�ƕ����̗Z���v���Ӗ�����B�l�b�g���[�N�̖{���́u�Ȃ��v���ƁA�܂�ʐM�ł���A�t�ɕ����̖{���̓R���e���g�ł���B���ɓ��{�̏ꍇ�A�f���R���e���g�̎��̓e���r�ɂ���B��ɏڏq���邪�A����ʁA�Y�Ɨ́A�\���́A�Z�p�͂Ȃǂ̊ϓ_����݂āA���{�̃R���e���g�̃R�A�̓e���r�ԑg�ł���B���������āA�l�b�g���[�N�ƃR���e���g�̌����A���邢�͒ʐM�ƕ����̗Z���Ƃ́A�ȒP�ɂ����A�e���r�ԑg��ʐM�l�b�g�ŃW���u�W���u�Ɨ��ʂł���悤�ɂ��邱�ƁA���{�����B
�@�ʐM�ƕ����̗Z���́A�ʐM�Ƃƕ����Ƃ̌��Ƃ��Ƃ��A�E�F�u�����f�W�^�������ŗ����T�[�r�X�i�ʐM�R���e���g������l�b�g���[�N�Ŏg���j�Ƃ��A���܂��܂Ȏ��ۂ��܂߂Č���邪�A�����͖{���ł͂Ȃ��B�t�ɁA�{�����Ƃ炦���ꍇ�A�e���r�ԑg�̃f�W�^�����ƁA�ʐM�Ԃ̑������Ƃ����{�̂Q��ۑ肾�Ƃ������Ƃ��͂�����ƕ����яオ���Ă���B
�@���l�ɃR���e���g�ƃv���b�g�t�H�[���̌����B����̓e���r�ԑg���R���s���[�^�ŃW���u�W���u�Ǝg����悤�ɂ��邱�Ƃ��B�u�e���r�̃f�W�^�����v���Ӗ�����B�f�W�^�������̈Ӌ`�Ƃ����ƁA�d�g�̌����g�p�ɂ��u���`�����l�����v�A�C���^�t�F�[�X���P�ɂ��u���掿���v����ɗ����A���ꂩ��R���s���[�^�Ƃ̌����ɂ��u�C���^���N�e�B�u�T�[�r�X�v������邱�Ƃ������B�����{���͂R�Ԗڂ̐V�����T�[�r�X�J���̂Ƃ���ɂ���B�e���r�ƃp�\�R���A�����ƃC���^�[�l�b�g����������Ƃ������Ƃ��B�f�W�^�������ɑ���A�����J�̃X�^���X�͓�������R���s���[�^�����ɂ������B���{�͂��̖ړI��헪���s���m�Ȃ܂܂Ȃ̂ŁA�������������Ȃ��B�����f�W�^���������ǂ����邩�́A���ɓ��{�ł́A�C���^�[�l�b�g���܂߂����f�B�A�̑S�̑������E����|�C���g�ł���A����I�ɏd�v�ȈӖ��������Ă���B
9.1.2�@�l�b�g���[�N����R���e���g��
�@97�N�̓d�C�ʐM�R�c��\�ɂ��ƁA95�N���_��30���~���x�̓��{���f�B�A�Y�Ƃ́A2010�N�ɂ�125���~�ɂ܂Ő�������Ɨ\������Ă���B�A�����J�̃��f�B�A�s�ꂪ96�N��120���~���x�ł��邩��A���{��2010�N�łقڌ����_�̃A�����J�̋K�͂ɂ܂ŒB����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�����ŏd�v�Ȃ̂́A���̓��ς���Ă����Ɨ\������Ă���_�ł���B���݂̓��{�̎s��ł́A�l�b�g���[�N�F�v���b�g�t�H�[���F�R���e���g�̎����\�����44�F23�F33�Ƃ���Ă��邪�A2010�N�ɂ�24�F21�F55�ɂȂ�Ǝw�E����Ă���B�l�b�g���[�N��20�|�C���g�����������A�R���e���g��20�|�C���g�㏸����Ƃ����̂��B
�@�ʐM�C���t������������A�������z�����ł��ɂȂ��Ă����Ƃ����͕̂K�R�ł��낤�B�C���t���Y�Ƃ������v��ۂ��A����Y�Ɖ����Ă���͓̂��ĉ��̋��ʌ��ۂ��B����������̓C���t���Z�p�����V����Ă���̂Ŏ��X�ƐV�K�������K�v�ƂȂ邽�߁A�����̌����Ƃ��Ă̎�����������Ă���̂ł����āA�Z�p���������āA������l�b�g���[�N�̐������i�߂A�C���t���Y�Ƃ����剻�𑱂���̂͐��F����Ȃ��B������ς���A���Ɛ���ɂƂ��ẮA�C���t�����v���[���ɋ߂Â��Ă����̂������ڕW�ƂȂ�B�u�C���t���Y�Ƃ̐����v����u�C���t���̔�Y�Ɖ��v�Ƃ������l�̋t�]�����߂���B
�@����A�R���e���g��55���ɒB����Ƃ����Ӗ��͉����B���݂̃R���e���g�ł���G���^�e�C�����g��j���[�X�Ƃ��������삪���x�������Ƃ���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B�����������܂��̂́A�d�q������ł���B������Ƃ����C���[�W�������Ƃ���A�T�C�o�[����ƌ����Ă��悢�B���Z��V���b�s���O�A��Â⋳��A�����čs���A�Ƃ���������܂Ō����Љ�ōs���Ă����������C���^�[�l�b�g��ōs���A����炪�R���e���g�Y�Ɖ�����Ƃ������Ƃ��B
�@���f�B�A����Ƃ��Ă݂Ă��A�R���e���g��d�q��������ǂ��L�������d������邱�ƂɂȂ�B�C���t�������Ƃ����������̍s������A�����p�����Y�ƁE����E�����E�s���̉~�����Ƃ����A����Η��p���̍s���A���{�S�̂��֗^���鐭���W�J����ɂȂ�B�A�����J���{��90�N��㔼�ɓ���A�l�b�g���[�N���ǂ���邩����A�ǂ��g�����ւ̍s���ɖ��m�ɃV�t�g���Ă���B�f�W�^������̈ʒu�Â���D��x�̓_�ŁA���{���{�̓A�����J�ɂ��Ȃ萅���J�����Ă���B
2�@���f�B�A�������[�g
2.1�@���[�g�̊g�[�ƍĕ��z
�@�A�����J�͎����f�c�o��98�N�� 3.9�������������A�A�o�������������A�C���t���̋�������Ȃ��܂܂ɐ��ڂ��Ă���B���{�̍����Ԏ��͓��{�ɔ�ׂĂ��Ȃ菬�����B����A���{�͌o�Ϗ��܂��S���Ȃ����̂́A�X�g�b�N�͂���B���~����14���i�A�����J�͂T���j�A�ΊO���Y��9000���h���i�A�����J�̓}�C�i�X8000���h���j�B���̃X�g�b�N���������A���̃f�W�^������p�ӂ��邱�Ƃ����{�̉ۑ�ł���B
�@���f�B�A�ɗ���鎑�����[�g���ǂ��L���邩���d�v���B���Ƃ��e���r�̖����͊�Ƃ���̍L�������Ő��藧���Ă����B�������A�L���������n�܂�A�ƒ납��̒��ڂ̎x�������[�g���������A�G����V���̂悤�Ȏ����\���ɂȂ��Ă���B�ʐM�����l�ɁA���Ă͊�Ƃ�ƒ납��̗��p���Řd���Ă����̂��A�C���^�[�l�b�g���R���e���g�̗��ʎ�i�ɂȂ������߁A�L���������悤�ɂȂ�A������G�������Ă���B���̂悤�Ȏ����`�����l�����ǂ̂悤�Ɋg�[���A�|�[�g�t�H���I���ǂ��g�ݗ��Ă邩���A�P�̉ۑ�ł���B
�@���f�B�A�Y�Ƃ̓����ł̕��z������ȃ|�C���g���B�����I�ɂ݂�A�l�b�g���[�N����R���e���g�ւƂ����V�t�g���\�������B�����A���݂͂܂����̍\����������Ƃ������Ƃ��Ăł��������Ă͂��Ȃ��B�͍���Ԃ��B���f�B�A�Y�Ƃɗ���鎑�����C���t������R���e���g�֔�d���ڂ��Ƃ��Ă��A��������荞�ޓ����ƁA������ĕ��z����d�g�݂��܂������Ȃ��B���Ƃ��C���^�[�l�b�g��Ƃ����p�҂���z���グ�����J�l���g�R���e���g��Ƃɕ��z����̂��A�|�[�^���ŃR���e���g�Ɉ������q�̃J�l�̈ꕔ���C���t�����p���ɉ̂��A�Ƃ��������Ƃł���B
�@���̂���99�N�ɂ́A�l�b�g���[�N�A�v���b�g�t�H�[���A�R���e���g�̂ǂ̕���ł������Ōڋq���l�����A���܂����q����͕ʌ��ŃJ�l�����A����𒇊Ԃŕ��������Ƃ����`�̃r�W�l�X���A�����J�𒆐S�ɍL����A���̂��߂ɋƎ���܂������Ƃ̍����E��g�A�܂萂���������i��ł���B�A�����J�̃f�W�^���ƊE�ł͋K�̗͂��v��ǂ��A���Ǝ�̍����A�܂萅��������90�N��ɓ����Đi�߂��A���ꂪ90�N��㔼�ɂ͓��{�ɂ���щ��Ă����B����A90�N��O���ɐ��������������͂��炭�������Ă����̂����A�C���^�[�l�b�g�E�r�W�l�X���{�i������ɂ�A�l�b�g���[�N�A�v���b�g�t�H�[���A�R���e���g�̑����W�J�Ōڋq���͂����ޓ������������Ȃ��Ă���B
2.2�@��ƃ��[�g
�@��Ƃ���̂��J�l�ɂ́A�L���������������B�܂��L����͊�Ƃ��R���e���g�ɏo�����������AGDP��ł݂�ƃA�����J�Q���A���{�P���B���z�x�[�X�ł͓��{�̂S�{�ɂȂ�B���f�B�A�s�ꂺ����GDP��A�����J12���A���{�U���A���z�x�[�X�łS�{������A����Ɍ������i�D���B
�@�������C���^�[�l�b�g�L���̎s��́A98�N�ł݂�ƁA�A�����J�Ɠ��{�͋��z�x�[�X��20�{���炢�̍�������B�d�q������͍���Ƃ��L�����S�̑̎��Ȃ̂ŁA���{�̓C���^�[�l�b�g���L���}�̂Ƃ��Đ헪�I�ɐ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ً͋}�̉ۑ�ƌ����悤�B���̂��߂ɂ́A�C���t��������i�߂邱�Ƃ��K�v�����A�����Č��ʓI�Ȃ̂́A���{���g���R���e���g�����҂ƂȂ邱�Ƃł���B�����J�Ɠd�q���{���B���Ƃ��C���^�[�l�b�g�Ŕ[�ł���ΐŋ����܂��Ă��Ƃ����{�������C���^�[�l�b�g���p�̓O�b�Ƒ����邾�낤�B
�@���ɏ�ւ̓����Ƃ��ďo�����J�l�����A99�N�ŒʐM�����ɂ��ƁA�A�����J��GDP��S���i35���~�j�A���{��2.3���i11���~�j�B���̊J���͑傫�����A�����Ȃ̂́A�A�����J��80�N��̕s�����ɂ����Ă����̐�������������ۂ��Ă����Ƃ������Ƃ��B����́A����������X�g���̎�i�ł��邱�Ƃ����m�ɔF������Ă����Ƃ������Ƃ��B�����͂����邽�߂ɁA�s�v�ȕ������B���̂��߂̃f�W�^���ł����āA���̌�����ꂪ�����͂̌����Ƃ����F�����蒅�����B�ď����Ȃɂ��Ƃ��̐����͏㏸�𑱂��Ă���A���ʐM�ւ̓������o�ϐ��������������グ��\���ɂȂ��Ă���B
�@����A���{�̓o�u����A���̐������ቺ�����B�s�����������������炷�Ƃ������Ƃł���A�Ȃ���ɓ������邩�Ƃ�����Ƒ��̖ړI�ӎ����͂����肵�Ă��Ȃ������B��̌��ʁA���ԊǗ��ґw�̎��Ƃ��������邱�Ƃ��莋����X�������݂�ꂽ�B����𐭍��I�Ɏ蓖����͍̂���B��ƈӎ����Ⴏ��ΐŐ��[�u�����Ă����_���B�t�ɁA��������͂����E����Ƃ������Ⴊ������ɂ�A���{�̑Ή����ς��B99�N�ɂ͊�ƈӎ����傫���ς�����Ƃ݂Ă悢�̂ł͂Ȃ����B
2.3�@R&D�ƃx���`���[
�@�A�����J�̃C���^�[�l�b�g�Y�Ƃ��x���Ă���͉̂����Ȋ����s��ł���B���{�͒��~���������Ƃ͂����A�a����ꂽ���������Z�@�ւ����ƂɌ������p�C�v�̂Ƃ���ł�������l�܂��Ă���̂ɑ��A�A�����J�͌l�̎����������ɓ�������Ă���B���_�A��Ƃɂ��x���`���[���������B�x���`���[�L���s�^���̓�����98�N��140���h���Ƃ����A�O�N��24�����ƂȂ��Ă���B
�@�l�b�g���[�N�A�v���b�g�t�H�[���A�A�v���P�[�V�����A�R���e���g���킸�A���̎����◘�v��������������������Ŋ������オ��A���̗̑͂����ɑ��Ђ����A�Ƃ���������������99�N�̃A�����J�s����x�z�����B���N�O�ɂ͕��������Ƃ��Ȃ���Ђ��R������d�b��Ђ�������A��x���������v�サ�����Ƃ̂Ȃ���Ƃ��₨�犔�������J���Ē��~�P�ʂ̎������z���v�サ���肷��Ƃ����A�����ꂪ�����ƂȂ��Ă���B
�@�������A���ʂ̃C���^�[�l�b�g�i�C�́A���т⎑�Y�Ɋ�Â������ł͂Ȃ��A�����ɑ�����҂��`�Â����Ă��鍂�l�ł��邽�߁A�o�u���Ƃ̎w�E���������B�Ƃ͂����A98�N�ɃA�����J�Ŋ��������J������Ђ�611�Ђ���A���{�̂V�{�ɂ̂ڂ�B���J�Ɏ���܂ł̕��ϔN���̓A�����J�T�N�A���{��29�N�Ƃ����B�����ȋN�ƂƂ���𗠑ł����鎑���`�����l�����A�����J�̍D�i�C���x���A���{�Ƃ̊i����ł���B
�@IT�Y�Ƃ��o�ς���������Ƃ����B99�N�U���̏����Ȃ̃��|�[�g�ŁA�f�C���[���������͍�N�ɑ���IT�Y�Ƃ��A�����J�o�ς̂W�����߂�Ƃ������Ƃ����������B�������A���ӂ�v����̂́A����ł��Ȃ��W���ł����Ȃ��Ƃ����_���B�A�����J�̍D���Ȍo�ς́A�uIT�Y�Ɓv�������炵���̂ł͂Ȃ��B�uIT�v�������炵�Ă���̂��B�����A�����A���Z�Ƃ������Y�ƑS�ʂɂ����āA����ƃ��X�g�����i�݁A���ۋ����͂��P�����N�������x���ɒB���A�o�ς��Đ������Ƃ������Ƃ��B
�@���{�ł��x���`���[�琬�������_�Ƃ��Ę_�����Ă���B�������o�ύĐ��̎�i�Ƃ��ăx���`���[�Ɋ��҂���Ƃ����̂͒��ӂ�v����B�̐S�Ȃ̂́A�����K��r�W�l�X���f����N���ς���̂��A�Ƃ������Ƃ��B�A�����J�͂����V����Ƃ�������̂����A���{���V����Ƃ����ׂ��Ȃ̂��A�����̉�Ђɓ����s�����Ƃ点��̂Ƃǂ��炪�����I�Ȃ̂��A�܂����߂̗]�n������B
�@����A�ʂ̈Ӗ��Ńx���`���[��Ƃ̈琬�͏d�v�ł���B�����I�ȈӖ����B���{�̕\�������͒U�ߏO�Ƃ������A�I�[�i�[�����ʂȏo������邱�Ƃɂ���Đ��藧���Ă����B�ŋ߁A�ǂ̉�Ђ��T�����[�}����Ɖ����Ă��邽�߁A�����ɗ���鎑���̃`�����l�������ɍׂ��Ă��Ă���B�R���e���g�̎����`�����l���̈ꕔ���l�܂��Ă��邱�Ƃł���A����͓��{�ɂƂ��Ă��Ȃ�[���Ȗ��ł���B
�@IT�Y�Ƃ̌����͂��錤���J���iR&D�j�̎����ɂ���肪����B�ʎY�Ȃɂ��AR&D�����̂f�c�o��̓A�����J���Q���A���{�͂R���ƂȂ��Ă���B�������A���{�̕��S�䗦�̓A�����J34���A���{23����10�|�C���g�̊J��������B�l�b�g���[�N�����ł͓��{�̓A�����J�ɑ��F�Ȃ����x�܂ŗ\�Z�K�͂��g�債�Ă���̂ɁAR&D�̔�d���Ⴂ�̂��B
�@����̓A�����J��IT���삪�R���\�Z�ɂ���Ďx�����Ă���ʂ������Ă���̂����A����ɁA�A�����J�͐��{�ƎY�ƊE�̘A�g�����{�ȏ�ɐ[���Ƃ������Ԃ��������Ă����ׂ����B��w�ƎY�ƂƂ̘A�g������ł���B���{�͊����̖������ے�I�Ɏw�E����Ă��邪�A�Y�w���̘A�g�Ƃ����_�ł͘������傫���Ƃ����̂������ł���B��Ƃ����ו��������X�����i�ނƂ���A��b�����ԂɊ��҂�������̂͌����I�ł͂Ȃ��BIT����͊����s��Ȃǖ��Ԃ̎����ł܂��Ȃ����Ƃ���{�ƂȂ��Ă�������A���{�ɂ͊�b�����ɑ���X�|���T�[�̖��������߂Ă������Ƃ����߂���B
2.4�@�ƌv���[�g
�@�ƒ납��̏��x�o�����f�B�A�ɂǂ��U������邩��������̒��ƂȂ�B�A�����J�̐������茳�ɂȂ��̂ŁA�����ł͓��{�ɍi���Ę_����B�������̒����ɂ��ƁA�S����ɐ�߂���ʐM�x�o�̔䗦�́A�ߋ�20�N�ԁA
4.7�`5.4 ���̊Ԃ��Ă����B�j���[���f�B�A�u�[���̍��ɂ��A�ƒ�̏��ʐM�x�o�̔䗦�͍��܂�Ȃ������B���̂��߁A���f�B�A�����l�����Ă��T�C�t�̃q���͂��܂��A��������ɋ������肪�������Ȃ�Ƃ����_���Ɏg���Ă����B
�@�Ƃ��낪�A���̂Q�N�قǁA���̐��l���}���ɏ㏸���Ă���B97�N�ɂ�5.9���ƂȂ��Ă���B�㏸�̎傽�錴���͌g�ѓd�b�̕��y�ł���B���ɒʐM��ɉ�邨�J�l�������Ă���Ƃ������Ƃ��B���̌�̃C���^�[�l�b�g�̐L�тŁA�܂��㏸���Ă���ł��낤�B�U���̃J�x��j���Ă��邱�Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B
�@�ƒ납��̏��x�o�������X���ɂ��邱�Ƃ͋ɂ߂ďd�v�ȃ|�C���g�ł���B���f�B�A�Y�Ƃ̐v�}��`�������Ŋ�{�I�ȗv�f���B�������Ȃ���A�����ɒ��ӂ��Ȃ�������Ȃ��̂́A�l�b�g���[�N�A�C���t���̂ق��ɂ��J�l������Ă���Ƃ������Ƃ��B�t�ɁA�R���e���g�̎s�������ƁA�}���K�̔��オ�����Ă�����A���邢�͉��y�b�c���L�єY��ł����肵�āA�R���e���g�Ɏq�������̂��J�l������Ă��Ȃ��Ƃ������Ԃ�����B���f�B�A�ւ̎������R���e���g����C���t���ɋz�������\�}�ł���A�ɂ߂ĕs���S���ƌ��邱�Ƃ��ł���B
�@�Ƃ��낪�A����ɍl���Ă݂�ƁA��҂͉��y�̂b�c��A�j���Ƃ������v����������R���e���g�����A�����̗F�B����l�̐��ɃL���[�R���e���g���������Ă���Ƃ������Ƃ��B�v���̕\���ɂ��Â������������A�F�B�Ƃ̂�����ׂ�ɂ��J�l�����Ƃɉ��l�����o���Ă���Ƃ������Ƃł���B����́A�N�������M���鎞��A���l�̃E�F�u�\���̎���̓�����\�����Ă���Ƃ�����ɓǂނׂ���������Ȃ��B
3�@�R���e���g�E�A�v���P�[�V����
3.1�@�R���e���g�Y�ƂƓd�q�����
�@�d�C�ʐM����d�C�ʐM���܂߁A�R���e���g�s��̓A�����J��2800���h�����x�ł���A���{�̂R�`�S�{�ƂȂ��Ă���B���̔����߂����f���Y�Ƃ��B�����ƋZ�p���W�����������n���E�b�h���č��������łȂ����E�s��𐧔e���A���̗͂��C���^�[�l�b�g����ɂ��������悤�Ƃ��Ă���B
�@���{�̎s��́A�f���S���~�A���y�Q���~�A�����i�V����o�Łj�T���~���炢�A�Ƃ�������ɂȂ�B�f���S���~�̂����R���~���e���r�ŁA�Q�[����5000���~�B�d�q������͂܂��l�O���W�u���ƌ����Ă悢�B
�@98�N�ŒʐM�����ɂ��A�d�q������̓A�����J�ł͖�1.2���~�ŁA���{��15�{�̋K�͂ɒB���Ă���Ƃ����BB to B�i��ƊԎ���j���AB
to C�i����Ҍ�������j���A�����J�ł͗��p������ɂȂ��Ă���B���̔w�i�Ƃ��āA���Ƃ��ƃA�����J�̒ʔ̂̎s�ꂪ���{�̖�60�{�̋K�͂�����A�Ђ���{�ł̓R���r�j�����y���Ă��āA������Ă��Ă����S�ŁA�l�����x�������Ƃ����y��̈Ⴂ�����낤�B
�@B to B��B to C��10�F�P�̋K�͂Ƃ����A�Y�ƊE�����ł̃g�����U�N�V���������݂̃C���^�[�l�b�g����̎厲���Ȃ��Ă���B�����čŋ߁AC
to C�Ƃ������ׂ��A�l�ǂ����A����҂ǂ����̎�����}�g�債�Ă���B�I�[�N�V�����T�C�g�̐����ł���B�C���^�[�l�b�g����̃g�����U�N�V�����́A���ꂪ�ł��傫���Ȃ�Ǝw�E������Ƃ�����B
�@�Ȃ��A�A�����J�ł͓d�q��������蒅�������̂悤�Ȉ�ۂ��邪�A���ԂƂ��Ă݂�A�{�i���͂܂����ꂩ��ł���B���݂̓d�q������͊T���āu�����̏�v�ł���B��Ǝ���̎�t�E�������E�F�u�T�C�g�ōs����悤�ɂ����A�Ƃ����i�K���B���̉��̏�A�܂�u�Ɩ������̏�v�͂܂��{�ԂƂ͂����Ȃ��B�ɊǗ��A�����Ǘ��A�����Ǘ��Ƃ������r�W�l�X�{�̂��l�b�g���[�N������Ƃ����A�C���^�[�l�b�g�ȑO���炸���Ǝ��g�܂�Ă����u�Y�Ƃ̏�v���C���^�[�l�b�g�ōč\������i�K�����ɗ���B
�@��������i��C���^�[�l�b�g�n��ƁA���Ƃ��|�[�^���T�C�g�ł���Ƃ��A�d�q���Д̔��ł���Ƃ��A���������V���T�C�o�[��Ƃ��r���𗁂тĂ��邪�A�ނ�����̂悤�ȃ��A���r�W�l�X�̑������}���ł���B����A�]������̃��A����Ƃ̓C���^�[�l�b�g������i�߂Ă���B�T�C�o�[�ƃ��A���̑o�����̃A�v���[�`�����낻��h�R���悤�Ƃ��Ă���A�e�r�W�l�X����ŒN������������������̂��A�܂������͌����Ă��Ȃ��B����̓A�����J�����łȂ��A�S���E�I�ȏł���B
3.2�@�|�[�^���ƃG�[�W�F���g
�@�d�q������̂Ȃ��ł̃|�[�^���������������i��ł���B���������ł���B�|�[�^���̓����́A�����ɏo�Ă���T�C�g������҂ɑ��ĕҏW���Ă��@�\���l�����铮�����B�u���E�U�⌟���G���W��������Ђ����ɁA�R���e���g���͂����݁A�����Ɍl���͂��������Ƃ��Ă���B
�@�A�����J�̃C���^�[�l�b�g�̃R���e���g�́A�n���E�b�h�̋Z�p��Y�Ɨ͂�w�i�Ƃ��Ȃ�����A���l�ȃx���`���[��Ƃ����S�ƂȂ��Ă���B�T���t�����V�X�R��j���[���[�N���{���n���B�T���t�����V�X�R�ł̓}���`���f�B�A�K�E�`�ƌĂ��n�тɎႢ�N���G�C�^�[���W�܂��Ă���B�T���t�����V�X�R�̓�ɍL����V���R���o���[�̓n�[�h�E�F�A�n�ŁA���܂�}���`���f�B�A�K�E�`�̃R���e���g�n�����̔������ƂȂ��Ĉ������낤�Ƃ��Ă���ɂ���B
�@���������R���e���g�n�x���`���[�́A�R�`�S�l�Ă��ǂőn�Ƃ���Ⴊ�����B���ꂼ��Z�p�A�f�U�C���A�t�@�C�i���X�Ȃǂ�w�i�Ɏ��������l���W�܂��āA���b�N�o���h�����m���Ńr�W�l�X���n�߂�B���܂��s���Ȃ���v���C���[��ւ�����A�o���h�����U���č��Ȃ������肷��B��啪��Ɏ��M������A�y��������Ă�����B������������A���{�̎�҂ł��\���ɂ���Ă�����Ǝv����B���ɓ��{�ł��a�J�E�G�Ō��C�ȃx���`���[�����X�Ɛ��܂�Ă��Ă���B���{�̖��́A�x���`���[�L���s�^���Ȃǂ���𗠑ł����鎑�����[�g���s�����Ă��邱�Ƃɂ���B
�@���āA�|�[�^�������́A�ҏW�@�\���v���̐���Ƒ������Ƃ����A��O��y���̕ҏW������悤�Ȃ��̂��Nj�����Ă���̂����A�����ɁA���p�Ҍl�̃\�t�g�E�F�A�ł��̂悤�ȋ@�\���������悤�Ƃ�������������B�l�p�̃G�[�W�F���g���B�����̍D�݂��G�[�W�F���g�\�t�g�ɗ��������Ă����A�ނ��������̏���T���A�I�сA�������A��������B�|�[�^�������ƃT�C�g���������G�[�W�F���g���g���Ƃ���A������͔�����G�[�W�F���g���J��o���A���㗝�\�t�g�����ڌ�����B���̏������錤�����ł����̂悤�Ȏ�@���������Ă���B��Ƃ������͂����ނ̂��A�����T�C�g����������I�Ԃ̂��A�㗝�l�̎�ł��̍j�������n�܂�B
3.3�@�f��ƃe���r�ƃP�[�^�C
�@���ẴR���e���g�S�̂̓������Ƃ炦��ƁA�A�����J�͉f��̍��ł���A���{�̓e���r�̍��Ƃ������Ƃ�������B�A�����J�͉f����ږ���Ƃ����ϓ_����S�����f�B�A�Ƃ��ĕ��y�����Ă����Ƃ����w�i������A�����e���r�̓n���E�b�h���x���Ă���ʂ������B���{�̏ꍇ�͒��������X���̉f����e���r���x���Ă���A�\���Ƃ��ċt�ɂȂ��Ă���B
�@���{�̉f���\�t�g�����98���̓e���r�ł���A���ۓI�ɋ����͂������Ă���̂��A�j���ƃQ�[���̕���ł���B�����̏��s�����猩�Ă��A�g�ŋώ��̕������e���r�ɍ����Ă���ʂ��傫���B�����ł͕\���Ȃ����A�������e���r�̂��Ƃ�[����Ɏv���Ă���x�����Ƃ������A�n�}���x�Ƃ����_�ŁA���{�͐��E�̒��ł����قȍ������ւ��Ă���B
�@�����Œ��ӂ�v����̂́A�n���E�b�h�͏���ɏo���オ���Ă����n��ł͂Ȃ��A���Ȃ萭���I�ɗU������Ă����Ƃ��������ł���B���Ƃ���70�N��Ƀe���r�ǂ��ԑg���������ԑg�𗬒ʂ������肷�邱�Ƃ𐧌������肵�āA�n���E�b�h�Ɏ�����l�ށA�Z�p���W�����������悤�ɂ��Ă����B���������ăA�����J�̃e���r�Y�Ƃ́A�R���e���g�Y�ƂƂ������A�l�b�g���[�N�Y�ƂƂ��Ă̐F�ʂ������B���{�̏ꍇ�͕ʂɉ����U�����Ă��Ȃ������̂ŁA�e���r�i��蕪���n��g�j���R���e���g�Y�ƂƂ��đ傫���Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B
�@�����ē��{�̂�����̓����́A�g�ѓd�b�̕������ُL����悤�Ȕ��B���Ƃ��Ă��Ă���_�ł���B99�N���ɂ��āA���{�̌g�ѕ��y����40���ɒB���A25���Ă��ǂ̉��Ċe���ɑ卷�������i78���̃t�B�������h�Ƃ�������n�т͂��邪�j�B����ɂ������āA�����ł͕\��Ȃ��悤�Ȃ����܂����g�����ݕ����ڗ��悤�ɂȂ����B
�@���w�����u���C���h�^�b�`�Ń}�V���K���̂悤�ɕ����𑗂��Ă���B�K���O�������E�F�u��̏����X�p�Ō������Ă���B�����ł͌����Ȃ����i���B�P�[�^�C���C���^�[�l�b�g�[���Ɖ������Ƃ͖����ł���A�C���^�[�l�b�g�̕��y���Ō�o��q����Ƃ������{�́A��N�w����}���ɐ��l���グ�Ă����\��������B�������A���̑O�ɍ����ė���ŃL�[�{�[�h��@���O�j�I�Ȋi�D�ł͂Ȃ��A�X������Ȃ���E��̐e�w��{�ő��삷��y�₩���ŁB
3.4�@�R���e���g�헪
�@���{�̉f������͑����ȗA�����߂����A�Q�[����A�j���͖�20�{�̗A�o���߂��B���{�ł��悤�₭�Q�[����A�j���������͂���Y�ƂƂ��Ē��ڂ����悤�ɂȂ��Ă������A�R���e���g�Y�Ƃ����̋K�͂���݂�ǒn��ł���A�Y�Ɛ����I�ȈӋ`�͂����傫���Ȃ��B�]�����ׂ��́A���̕�����^���B�Ⴆ��99�N�ɃA�����J�ł���O�̃u�[���ƂȂ����|�P�����̂������ŁA�A�����J�̎q�������͓��{����o���A���{�̐H�ו��╗�����J�b�R�������̂Ƃ��Ď���Ă���B�n���E�b�h�f��������l�X���A�����J�I������ɓ���A�����J���i���B����͏]������A�����J�̊�{�헪�����A���{�̓Q�[����A�j�����f��̖������ʂ����B
�@�R���e���g�̍��ۗ��ʂ�����c�_�́A����̖��ɓ˂�������B���ɓ��{��TOEFL�̐��т��A�W�A�ʼn��ʂƂ����[���Ȏ��Ԃɒ��ʂ��Ă���ɂ�������炸����Ȃ̂��C�ɂȂ�i������C���^�[�l�b�g�͉p�ꕶ�����A�����E�q���Y�[�E�C�X���������Ɏx�z�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����\���̕�����������������̂����j�B���̓_�t�����X�͉p�ꕶ���ւ̑R�ӎ����ނ������ɂ��邪�A�ŋ߂���ȏ�ɉf���\���̋Z�@�╶�̂Ƃ��������̂ɑ��i�[�o�X�ɂȂ��Ă���B�C���^�[�l�b�g���f�����f�B�A�����āA�\���̍������Ȃ��Ȃ�ƁA���悢��A�����J�ɂ�镶���e���̋��ꂪ��������тт邽�߂��B
�@���E�̉f���͍���n���E�b�h�\���̂ق��ɂ͓��{�Q�[���\�����������Ȃ��B�Q�[���̓f�W�^���̃C���^���N�e�B�u�\���ł��邩��A�C���^�[�l�b�g��ł̕\���Z�@�̓y��ɂȂ�B�d�q������̕\���x�[�X�ƂȂ�_�ŁA���{�̍��Ǝ��Y�Ƃ��čł���Ȉʒu���߂�B���̍���́A�q�����f���𗝉�������\�������肷��\�͂ł���B�}���K��ǂ݂��Ȃ��́A�Q�[���ɂ͂܂荞�߂�͂Ƃ��������̂��B���{�̏����͂��̔\�͂��ǂ���݁A�������邩�Ɉˑ�����B
�@�Ƃ��낪�A�����J�ł͂Q�N�قǑO����C���^�[�l�b�g��ł̃Q�[���i�l�b�g���[�N�E�Q�[���j�������オ���Ă���B���̂Ƃ���ۋ��V�X�e���Ȃǃr�W�l�X���f�����m�����Ă��Ȃ�����Y�ƂƂ��Ė{�i���͂��Ă��Ȃ����A������}������ƁA�f���\���̃R�A�����ׂăA�����J�����邱�ƂɂȂ�B
�@�A�����J���C���^�[�l�b�g�\���B�����邱�Ƃ��ł���v���Ƃ��āA�d�b�̒�z�������������邱�Ƃ��ł���B��z�Ƃ����͎̂g���قǃg�N�Ƃ������Ƃł���A�R���e���g����^�C�v�ł���B�]�ʐ��̓R���e���g�}���^���B���{�ł��ʐM��z���������ׂ��Ƃ����c�_������ɂȂ��Ă������A������Y�Ɛ���Ƃ�����蕶������Ƃ��Ă̕K�v���̕��������B
�@���āA�R���e���g����̒��Ƃ��āA�����ԑg����ȑΏۂƂ�����e�K��������B���̋���́A�e���̕����I�E�����I�Ȕw�i�ɂ���ĈقȂ�B�Ⴆ�t�����X�͓O�ꂵ�����ڋK���ł���A�A�����J���e�b�b�����m�Ȍ����̉��ɂ킢���ԑg�����K�����Ă���B����ɑ����{�́A�������Ǝ҂̎���Ή��ɈςˁA�قږ��K���Ƃ�����O�I�Ȑ��x���B�������x�̎��R�x��21���I�̍��ۋ����͂Ɋ�^������̂Ǝv���A���ƌ��͂ɗ��炸�Ƃ������Ɩ��Ԋ�Ƃ̎����p�ŎЉ�K�͂�ۂ�����Ƃ������{�̓����͐헪�Ƃ��Ċ���������B
�@�C���^�[�l�b�g���̓��e�K���ɂ��Ă��c�_���������B�A�����J��96�N�d�C�ʐM�@�ŒʐM�̓��e�K�����K�肵�����A���̊�������܂����Ƃ��āA97�N�V���ɂ͍ō��ق���ꕔ�ጛ�̔������o����Ă���B98�N10���ɂ͎����I�����C���ی�@�𐧒肵�����A������ጛ�Ƃ̑i�����߂����čٔ���̑������N�����Ă���B�C���^�[�l�b�g�W�҂̑����͍��Ƃ̉�����ɓx�Ɍ������A�ʏ�ǂ̍������{�ƈقȂ�A�����Ǒ��Ɋւ����͂����o������Ȃ������̏����݂���B
3.5�@�d�q���������
�@�e���̐���Ƃ��Ă̊S�́A�f���e���r����A�C���^�[�l�b�g��̃R���e���g�ւƋ}���ɃV�t�g���Ă���B�d�q������́A�Í��A�F�A�Z�L�����e�B��v���C�o�V�[�ی�ȂǁA���x��@���ɂ���ލ��Ɛ���Ƃ����ڂȊւ�肪����B�\���K���⒘�쌠�Ƃ����]���̃R���e���g������鐭�{�֗^���������Ȃ��B
�@�����ŃA�����J�̖ڕW�́A���̕���ł̋Z�p��Y�Ƃ̋�����w�i�ɁA���E�I�ȗD�ʐ����m�����邱�Ƃ��B���̂��߁A���Ƃ̉�����ł������r�����A���Ԏ哱�Ŏs������Ă������Ƃ��咣����B����A���B�͓`���I�ɃR���e���g������o�ς̘_�������ŕЂÂ��悤�Ƃ����A������肾�Ƃ���p����O�ʂɏo���āA�@���Ȃǂ̐��x�ɂ���ċK���E�ی삷��F�ʂ������B
�@���̂悤�ȏŁA98�N�ɂ͍��ۓI�Ȑ����������{�i�������B98�N�ɂ�WTO�AOECD�AAPEC�Ȃǃ}���`�̍��ە���Ŋt�����̒��������������Ă���B�A�����J�Ɖ��B�A���{�Ƃ̌ʂ̐��c���W�J����Ă���B���ۉ�c�ł̘b��̒��S�́A95�N�����ɂ̓C���t�������ł��������A���݂͓d�q������̐��x�t���[���ł���B
�@�A�����J�͌ʐ���̃X�^���X���P�����B���Ƃ��R���e���g���Y���l�̌���ƂȂ钘�쌠�͕ی삷�����A�e���ʼnۂ�����ł͔r���������Ƃ���ł���B98�N10���Ƀf�W�^�����쌠�@�𐧒�AWIPO���̔�y�Ɍ������葱��i�߂邱�ƂƂ��Ă���B�łɊւ��ẮA�d�q�I�Ɉ����n����鏤�i��T�[�r�X�ɂ͉ۂ��Ȃ��Ƃ����̂��A�����J�̎咣���B�C���^�[�l�b�g�ŗ��ʂ���R���e���g�̈ʒu�Â���v���C�o�V�[�ی��������ăA�����J��EU�͑Η����A���ۓI�c�_�ɔ��W���Ă���B
�@���B�嗤�͓d�q�����E�F�ɂ��Ă��K�����咣���鍑�������A�ƈɉp�Ȃǖ@�I�[�u�����Ă��鍑�������B����A�A�����J�͂����ł����Ԃ̎���Ή����d������X�^���X���F�Z���A���ۂɖ@�������Ă���̂͏B���x���ɂƂǂ܂��Ă���B�������A�M�͓d�q���{�𐄐i���Ă���A���̈�Ƃ��ēd�q�����̓������������Ă���B�K����̂Ƃ�����藘�p��̂Ƃ��Ă̐��B�����J���x�A�C���^�[�l�b�g�ł̎��ޒ��B�ȂǁA���{�ɂ��C���^�[�l�b�g�̗��p��d�q���{�̎����ɐϋɓI�ł���B�����A�Í��Ɋւ��Ă͈Í��͌R���Ƌ��Z�ɖ��ڂɊւ����̂ł��邽�߁A���Ǝ����Ƃ��Đ헪�I�Ɉ����Ă���B
�@�����ɂ��ē��{���݂�ƁA����v���C�I���e�B�̒Ⴓ�A�X�^���X�̕s���m���A�ӔC���݂̕s���m���A�Ȃǂ̖ʂŐS���Ȃ��B�X�̎{��͏ȗ����邪�A���Ƃ͎{�x���̖��ł͂Ȃ��A���ƂƂ��Ă̕��ς���̖��ƌ����悤�B
4�@�l�b�g���[�N�ƃv���b�g�t�H�[��
4.1�@����������96�N�d�C�ʐM�@
�A�����J�̃l�b�g���[�N���Ƃ͌������ɂ���B�i�}2�j
|